ドルの底打ちと夏の転換点──静かに進む「構造×季節性×イベント」の交差
2025年7月現在、市場には「ドルはこれから下がるだろう」という空気感が広がっています。しかし、それは必ずしも「今すぐドルを売るべき」という意味ではありません。実際には、ドルを巡る状況はもっと複雑で、多層的な視点が求められます。
本稿では、ドルに関する最新のマクロレポートをもとに、初中級の投資家でも理解しやすいよう丁寧に解説していきます。
1. ドルは「売られすぎ」ではないが、「買うべき」でもない
今のドル相場は、ちょうど「中間地点」にあるような状態です。売りが一巡しており、これ以上の下落は限定的かもしれない──しかし、積極的に買う理由もまだはっきりしない、という微妙な空気感です。
その理由のひとつが「季節性(シーズナリティ)」です。
2. 夏のドルは弱い? 季節性が教えてくれるパターン
過去10年以上のデータを見ると、ドルは7月中旬〜下旬にかけて弱くなる傾向があります。これは「季節性」と呼ばれる市場のパターンで、特にUSDJPY(ドル円)はこの時期に下がりやすいのが特徴です。
たとえば、ある年には7月の第3週から第4週にかけて、5日連続でドル安が進んだこともありました。こうした傾向は統計的にも裏付けがあり、多くのプロ投資家が取引判断に利用しています。
しかし、この弱さは永続しません。8月から9月にかけては、再びドルが強くなりやすい傾向もあります。
▶ ポイント:「季節性」とは?
「季節性」は、たとえば「本格的な夏は黒タイツが売れる」や「12月はゲームソフトが値上がりしやすい」などの「時期ごとの振れやすさ」を表す概念です。統計の見地からも気にすべきものです。
3. リスク資産全体に共通する「夏の変化」
この時期にドルが反発しやすくなる背景には、株式市場の「季節の転換」も関係しています。
一般的に、5月〜7月前半は株式市場が上がりやすい「強気の季節性」があります。しかし、7月後半から8月にかけてはそれが終わり、市場参加者がリスクを落とし始める時期になります。
特に8月・9月は、
- 株が売られやすい
- ボラティリティ(価格の振れ幅)が急に高まる
- 通貨市場でもリスク回避的な動きが増える
という傾向があります。これもまた、「ドルを売るにはタイミングが悪い」理由のひとつです。
4. イベントリスク──7月14日のCPI(消費者物価指数)
この夏における最大の注目イベントのひとつが、7月14日のアメリカのCPI(インフレ指標)です。
現在、市場では「インフレはすでに落ち着いた」という声が多く聞かれます。しかし、これはやや楽観的すぎるかもしれません。
というのも、関税(アメリカが一部輸入品にかける追加税)の影響がまだ統計に十分反映されていないからです。こうした関税が実際に物価を押し上げ始めるのは、施行から数週間後。
したがって、7月中旬〜8月にかけてのCPIで「思ったよりインフレが強い」というデータが出てくると、
- 「利下げは遠のく」
- 「ドルは再評価される」
- 「株や新興国通貨は調整」
といった流れが一気に進む可能性があります。
5. オプション戦略──AUD(豪ドル)に対する慎重な見方
レポートでは、AUDUSD(豪ドル/米ドル)について面白い指摘がありました。
豪ドルは中長期では買い要因が多く、
- 年金基金がドル資産に対するヘッジをまだ行っていない
- 経済構造的にはAUD買いにつながる材料が多い
という背景があります。
しかし、短期的には「0.68を超えるには無理がある」とも見られています。
結論──いまは「様子見」と「準備」の時間
現在のドル相場は、
- 季節性の転換点
- インフレ再燃のリスク
- リスク資産全体の変調
など、複数の要因が重なり合っており、非常に不安定な地合いです。
「ドルを売るには少し早い」「でも、ドルは底打ちしつつあるかもしれない」──そんな判断が必要な局面です。
焦って売買せず、今後のCPIや夏後半の動向を見ながら、戦術と構造の両面から備える姿勢が大切だと言えるでしょう。
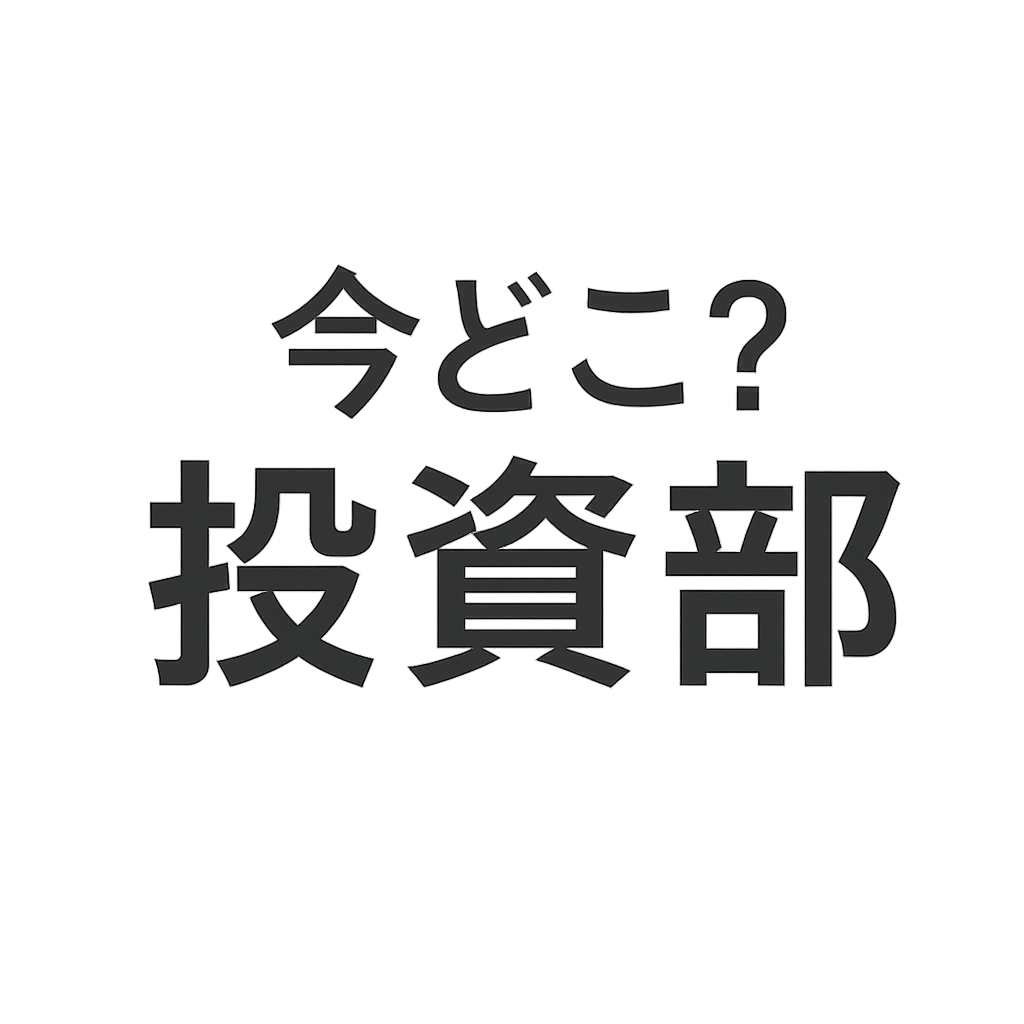

コメント