― 2025年7月時点の為替市場を読み解く6つの視点 ―
2025年7月現在、為替市場では「ドル安」という見方が大きく広がっています。
米国の財政赤字拡大や利下げ観測、そして海外投資家によるドルヘッジ需要など、ドルの構造的な下落要因が多数語られています。
実際、世界中の投資家やストラテジストが「ドルは中長期的に売られるべき」という意見を共有しており、これは近年まれに見る強いコンセンサスのひとつです。
しかし、注意深く観察してみると、ポジションサイズは驚くほど控えめです。
リスク資産のプロフェッショナルたちは、「ドルは下がると思うが、自分はフルポジションでは張っていない」と語ることが多く、実際のエクスポージャー(保有ポジション)は最大想定リスクの25〜30%程度にとどまっている例がほとんどです。
このように、相場の「ストーリー」と「資金の実際の動き(=フロー)」にズレがあるとき、相場は意外な方向に動くことがあります。
本稿では、現在の為替市場を読み解くための重要な6つの視点を、深掘りしながら解説していきます。
1. 「ストーリー」から「データ」へとシフトする市場の焦点
これまでの数年間、金融市場は「ストーリー主導」で動いてきた側面があります。
特に2020年以降のコロナ禍以降は、FRBのバランスシート拡大・財政出動・量的緩和などを中心とした「政策がすべてを動かす」時代が続いていました。
たとえば、以下のような短絡的な連想が広く信じられてきました:
- 財政赤字が拡大 → 景気刺激になる → 株価上昇
- ドル安になる → 仮想通貨が上昇する
- 金利が下がる → 成長株が有利
しかし2024年後半から2025年にかけて、市場の空気は徐々に変化してきています。
最近では「何を誰が言ったか」よりも、「その結果として実際に数字がどう動いているか」が重要視されるようになってきました。
たとえば:
- 米国CPI(消費者物価指数):インフレ率の基調を示すデータ
- 米雇用統計(NFP):労働市場の実体を反映
- 小売売上高、ISM指数:企業活動と消費動向を評価
これらの「ハードデータ」は、単なる予測や物語よりも強い影響力を持つようになっています。
今後は、たとえばCPIが再加速すれば「利下げは遠のく」→「ドル高」というシナリオが復活する可能性もあり、物語から現実への視線転換がより進んでいくと考えられます。
2. 主要通貨に見る構造変化とタイミングのズレ
ユーロ(EURUSD)
ユーロには現在、明確な「構造的買い材料」が存在しています。
特に、欧州の年金基金が米国株や米国債に対する為替ヘッジを積極化していることが、EUR買い/USD売りの流れを後押ししています。
また、ECB(欧州中央銀行)は以前であればユーロ高を牽制していたものの、今ではむしろ「ユーロはドルに代わるグローバル通貨候補」として肯定的に扱っているフシがあります。
しかし問題はタイミングです。EURUSDはすでに1.05 → 1.18まで急騰しており、短期的には「買われすぎ」の水準に達しているとの見方もあります。
構造的に強くても、ここからさらに買い上がるためには、新たな材料(たとえばCPIの鈍化やFRBの明確なハト派転換など)が必要となるかもしれません。
円(USDJPY)
日本円は現在、「構造的に買われにくい通貨」になっていると考える投資家が増えています。
主な理由は以下の通りです:
- 日銀が超低金利政策を継続し、実質金利がマイナス圏にある
- 米国の政策金利が高止まりし、実質金利がプラスである
- 日本の機関投資家(GPIFなど)は、米ドル資産に対して大規模なヘッジを行っていない
こうした背景から、円高に向かう材料が非常に少ないと見られています。
さらに、円買いポジションは「米国景気後退が明確になるまで報われにくい」という特殊な性質があるため、いまのようなソフトランディング基調の局面では不利といえるかもしれません。
カナダドル(USDCAD)
カナダドルは、構造的に強気の通貨として注目されています。
その背景には、カナダの年金ファンドが米ドル建て資産に対して為替ヘッジを強化しはじめたという動きがあります。
以前は「USDCADは米国株と逆相関するからヘッジ不要」と考えられていましたが、近年のデータではむしろ正の相関に移行しつつあり、「ヘッジなしではリスクが高すぎる」との判断が拡大しています。
さらに、カナダ中銀は比較的インフレに対してタカ派(利上げに積極的)であるため、政策面でもカナダドルは買われやすい状況にあります。
豪ドル(AUDUSD)
豪ドルは2024年後半からずっと「買われそうで買われない」通貨の代表格です。
主な要因は:
- RBA(豪中銀)がハト派的姿勢を継続している
- 中国経済の回復が期待外れに終わっている
- スーパーファンド(年金基金)が依然としてドル資産に対する為替ヘッジをしていない
とはいえ、裏を返せば「未執行の買い需要が眠っている」とも言えます。
一説によると、オーストラリアの年金がヘッジ比率を10%引き上げるだけで、1000億豪ドル規模のAUD買い(ドル売り)が発生する可能性もあります。
3. 新興国通貨とコモディティ市場の交差点
ブラジルレアル・南アランド(BRL、ZAR)
高金利の新興国通貨は、グローバルのボラティリティが低下している今、「キャリートレード」の魅力が再評価されています。
特にBRLやZARなど、相対的に金利水準が高く、政治的にも安定している通貨が買われやすい状況です。
しかし、市場にはすでに一定のポジションが積み上がっており、混雑感も出始めているとの声もあります。
この場合、急な金利変動やセンチメント悪化による巻き戻し(ポジション解消)が起きやすいため、慎重な運用が求められます。
原油(WTI)
一部の投資家の間では「WTIは40ドル台を目指す可能性がある」という声も聞かれます。
その背景には、以下のような要因があります:
- OPECプラスの減産効果が市場に織り込まれてしまった
- 夏季需要がピークを迎え、在庫が積み上がっている
- 中国・インドを中心とする需要が予想を下回っている
ただし、原油ショートはすでに混雑しつつある人気トレードであるため、反対方向へのショートカバー(売り戻し)リスクも忘れてはなりません。
4. まとめ:ポジションと物語のズレをどう捉えるか
2025年7月の為替市場では、「語られているストーリー(ドル安)」と「実際のポジションサイズやフロー(実需)」の間にズレが見られます。
こうしたズレこそが、相場変動の原動力となり得る重要なシグナルです。
多くの市場関係者がドル売りを語りながら、まだ十分にポジションを持っていない状況であれば、何かのきっかけで一気に動き出すことも考えられます。
これからは、「ストーリーを信じること」よりも、「誰が、なぜ、どれだけの資金を、どのタイミングで動かすか」に注目することが、投資成果に直結していくのではないでしょうか。
引き続き、ヘッジ比率の変化、政策決定会合、経済指標、そして各国ファンドの資産配分の動きに注目しながら、市場の呼吸を読み解いていきたいと思います。
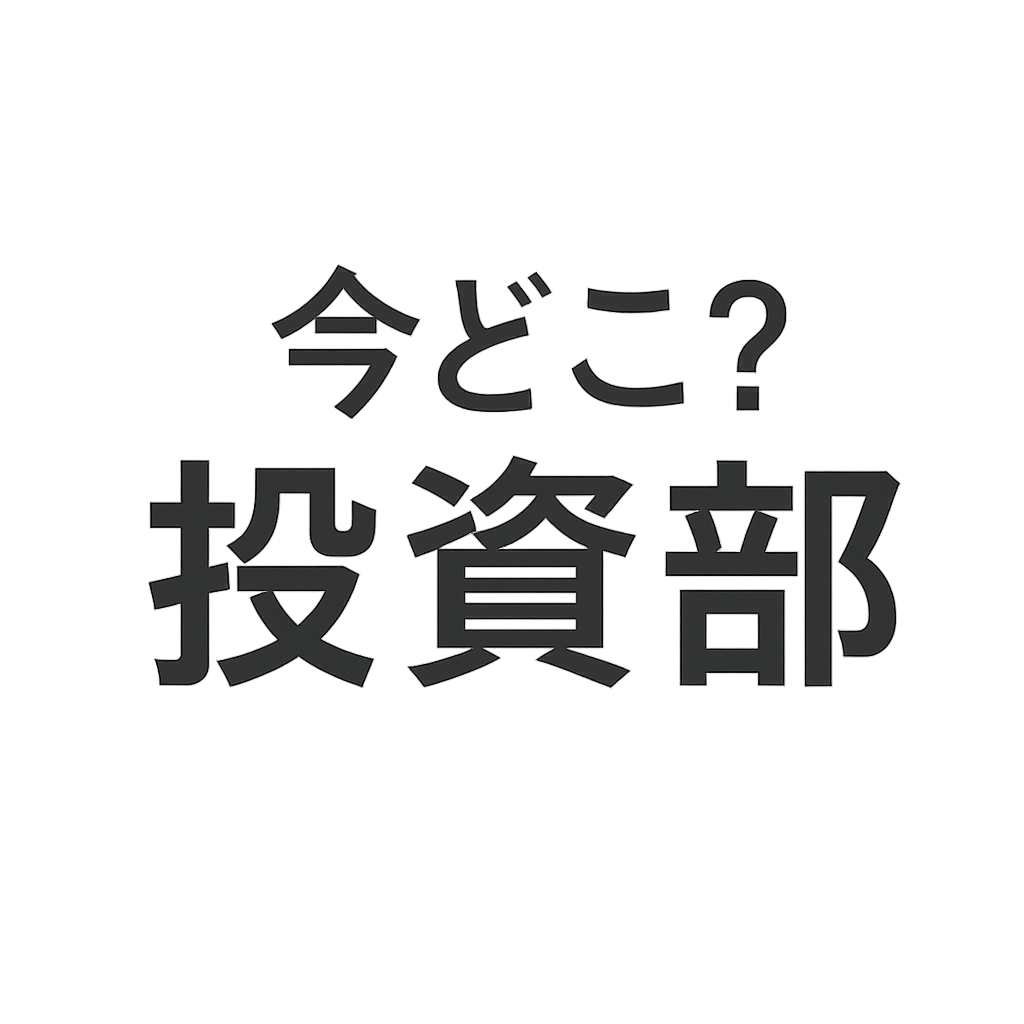


コメント